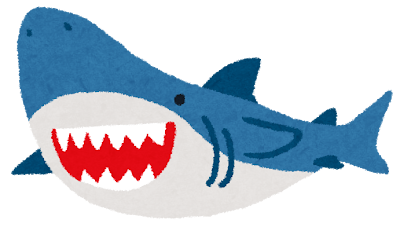ある土曜の朝、彼は友人と共にシドニーのノーザンビーチにあるロングリーフへサーフィンに出かけました。バトラーさんが海から上がって数分後、仲間のサーファーであるマーキュリー・シラキスさんがホホジロザメに襲われ、命を落としたのです。
「私たちは少し動揺しています」とバトラーさんは認めます。マーキュリーさんと彼の双子の兄弟マイクさんは地元ではよく知られた存在だったと付け加え、「いつも挨拶を交わす仲でした」と語りました。
この死亡事故は、オーストラリアの海で海水浴客の安全をどう守るかという、長年にわたる繊細な議論を再燃させ、ニューサウスウェールズ(NSW)州に再び注目が集まることとなりました。
州当局はサメによる襲撃リスクを軽減するため、様々な対策を講じていますが、その中で最も有名かつ物議を醸しているのが、毎年夏に多くのビーチで設置される「シャークネット」です。
自然保護活動家たちは、このネットは有益どころか害悪だと主張します。人気のサーフポイントにサメが到達するのをほとんど防げず、他の海洋生物に甚大な被害を与えているというのです。しかし、恐怖を感じる多くの海水浴客は、もう一つの防護策としてネットに愛着を持ち続けています。
サメ襲撃による死者数が世界最多のオーストラリア
オーストラリアには世界有数の美しいビーチがあります。人口の80%以上が沿岸部に住んでおり、早朝の海水浴やサーフィンは何千もの人々にとって日常的な習慣です。
しかし、その日々の習慣がますます危険になっていると感じる人々もいます。
66歳のシドニー在住の彼は、子供の頃、漁師が巨大なホホジロザメを釣り上げているのを呆然と眺めていたことを覚えています。当時は、現在保護種となっているサメもまだ合法的に狩猟できた時代でした。
尾で吊るされたこれらの死骸を見るのは「不吉な」気持ちになったと彼は振り返りますが、恐怖は感じませんでした。サメは深海の生き物であり、自分がサーフィンをするのは浅い湾だと考えていたからです。
しかし5年前、彼の娘アニカさんがグレートバリアリーフでフリーダイビング中にオオメジロザメに噛まれました。彼女は一命を取り留めましたが、この出来事をきっかけにクレイニーさんはサメに不安を抱くようになり、襲撃事件に関する派手な見出しを見るたびにその不安は増大しています。
「こういうニュースが引き金になって…パニックになります」と彼は認めます。
シドニーで過去60年間にサメの襲撃で死亡したのは、「マーク」さんの他に2022年の英国人ダイバー、サイモン・ネリストさんだけで2人目ですが、この街のビーチを日常的に利用する人々にとっては、ほとんど慰めになりません。
「以前はたまに黒い影を見かけることがあっても、それはイルカだったかもしれませんでした」とクレイニーさんは言います。「今では、しょっちゅう見かけます」。
世界で最も危険な2種、ホホジロザメとイタチザメを含むいくつかのサメがオーストラリアの海域で様々なレベルの保護対象となった後、サメの数が爆発的に増えているのではないかと懸念する声もあります。
サメの個体数に関する研究はほとんどなく、断定的なことは言えませんが、専門家は目撃情報の増加が必ずしもサメの数の増加を意味するわけではないと主張しています。
環境専門家は、海水温の上昇がサメの遊泳や摂食パターンを変化させている可能性を示唆しています。しかし研究者たちは、目撃情報の増加は主に、海に入る人の増加によるものであり、それがソーシャルメディアによって増幅されていると指摘しています。
オーストラリアでサメに噛まれる可能性は依然としてごくわずかです。溺死する可能性の方が数千倍も高いのです。しかし、この国がサメ襲撃のホットスポットであることは事実です。

国際サメ攻撃ファイル(International Shark Attack File)によると、サメに噛まれる件数では人口が13倍のアメリカに次いで2位ですが、死亡事故の件数では世界最多です。
このデータベースは「挑発されていない」事故のみを追跡しており、スピアフィッシングなどの活動によって人間が誘発した可能性のあるものは除外されていますが、オーストラリアでの記録されたすべてのサメとの接触に関するより完全なデータベースは、タロンガ保護協会によって維持されています。
それによると、サメによる襲撃はここ数十年で概ね増加傾向にあります。今年だけですでに4件の死亡事故が発生しており、すべてが挑発されていないものでした。
「プールにナプキン」のようなネット
NSW州は、最も古いサメ対策であるシャークネットの使用を縮小する試みを開始しようとしていた矢先に、今回の死亡事故が発生しました。
シャークネットはNSW州で1937年から使用されており、現在では通常9月から3月にかけて51のビーチに設置されます。クイーンズランド州を除き、現在もネットを使用しているのはNSW州だけです。
ビーチ全体を封鎖することは不可能です。海の状況はあまりにも強く、ネットは簡単に流されてしまうでしょう。
代わりに、シャークネットは約150mの長さで、水面から数メートル下に設置されます。海底に固定されていますが、底には達していません。そのため、サメはネットの上、下、周りを通り抜けることができます。
州政府は、シャークネットは「海水浴客とサメを完全に隔てるためのものではなく」、岸に近づくサメを「捕獲することを目的としている」と述べています。
しかし、ペピン=ネフ教授のような研究者は、ネットはあまり効果的ではなく、リスクを実際に減らすというよりは安全であるという幻想を与えているに過ぎないと言います。
彼らは、ネットにかかったサメの40%が、実際にはビーチ側から外に出ようとしているところを発見されていると指摘しています。
多くの批評家は、ネットが残酷であるとも言います。
「これらはサメや魚を捕らえるために作られており、その効果は絶大ですが、悲しいことに全く無差別です」と、撮影監督兼海洋探検家として長年これらのネットを記録してきたクロップ氏は語ります。
昨シーズン、NSW州のネットにかかった動物の約90%が標的種ではなく、その中には絶滅危惧IB類に指定され、ほとんどおとなしいシロワニが11頭含まれていました。東海岸沿いのネットには、毎年熱帯地方との間を回遊するザトウクジラも頻繁にかかります。
「イルカ、カメ、魚、エイなどを捕獲します…そして、もしそれが空気呼吸をする哺乳類や爬虫類であれば、時間内に解放されない限り、それは死刑宣告です」とクロップ氏は言います。
ペピン=ネフ教授は、ネットで死んだ動物が逆にサメをビーチに引き寄せる危険性があると考えています。
「他の魚がネットにかかると、彼らは暴れて水中に振動を発します。それはまるでディナーベルを鳴らすようなものです」とペピン=ネフ教授は言います。
一般市民はサメを警戒していますが、ネットへの支持は薄れつつあるようです。
ペピン=ネフ教授が2年前にボンダイビーチで行った調査では、回答者の4分の3が、シャークネットが撤去されてもビーチで泳ぐと答えました。同様の数の人々が、もし襲撃が起きても州政府を非難しないと述べました。
ドローン、アプリ、そしてサメ対策ウェットスーツ
シャークネットには代替案があります。
クイーンズランド州とNSW州は、餌をつけたフックを固定する「ドラムライン」も使用しています。NSW州では、致死性の低い「スマート」ドラムラインを使用しており、サメがかかると当局に通知が送られ、職員が駆けつけてタグを付けてから解放または移動させます。
西オーストラリア州には、より網目の細かいネットで沿岸の小さな部分を完全に区画する「エコバリア」があり、サーファーではなく遊泳者に対してより良い保護を提供しつつ、海洋生物への害を最小限に抑えています。
一部のサーファーは電磁式のサメよけバンドを使用しており、「噛みつきに強い」と謳われるウェットスーツさえ存在します。
また、タグ付けされたサメを追跡し、ビーチに近づくと近くの遊泳者に警告するアプリもあります。
そして、ますます多くのドローンが海域のパトロールに使用されています。NSW州では、現在50のサーフポイントで300機以上が運用されており、その数は今後も増える見込みです。
「ドローンは空からの目です。水際から誰かが見ていて、ひれを見つけるかもしれない、というレベルではありません」と、ドローン操縦士のアイザック・ヘイルズさんは言います。
彼のドローンのブーンという音は、彼が今日飛行している場所の人々にとって特に安心感を与えています。ここはディーワイ、最近の死亡事故が起きた湾の近くのビーチです。
しかし、資金の制約により、このプログラムはビーチが混雑する学校の休暇中にしか実施されていません。
「もしサメを発見すれば、ライフガードに伝え、彼らがジェットスキーでサメを積極的に追い払ったり、人々を避難させたりすることができます」
「これは単なる受動的な対策ではありません」
代替のサメ対策技術の出現や、ネットが他の海洋生物に与える影響を訴えるキャンペーンを受けて、この夏、シドニーの3つのビーチでネットを設置しないことが決定されていました。
しかし、その計画はシラキスさんの死亡事故に関する報告を待つため、すぐに保留されました。
彼の家族は声明を発表し、彼はリスクがありながらも海を愛していたと述べ、彼の死を「悲劇的で避けられない事故」と呼びました。
しかし、当局はそれでもなお怖気づいています。
「ネット撤去まであと一歩のところまで来ていたのに、この悲劇的な事故が起きてしまいました」とクロップ氏は言います。
「シャークネットを撤去した直後に死亡事故が起きる、そんな人物には誰もなりたくありません。自分の良心にその責任を負いたくないのです」